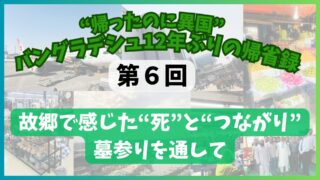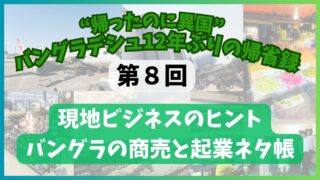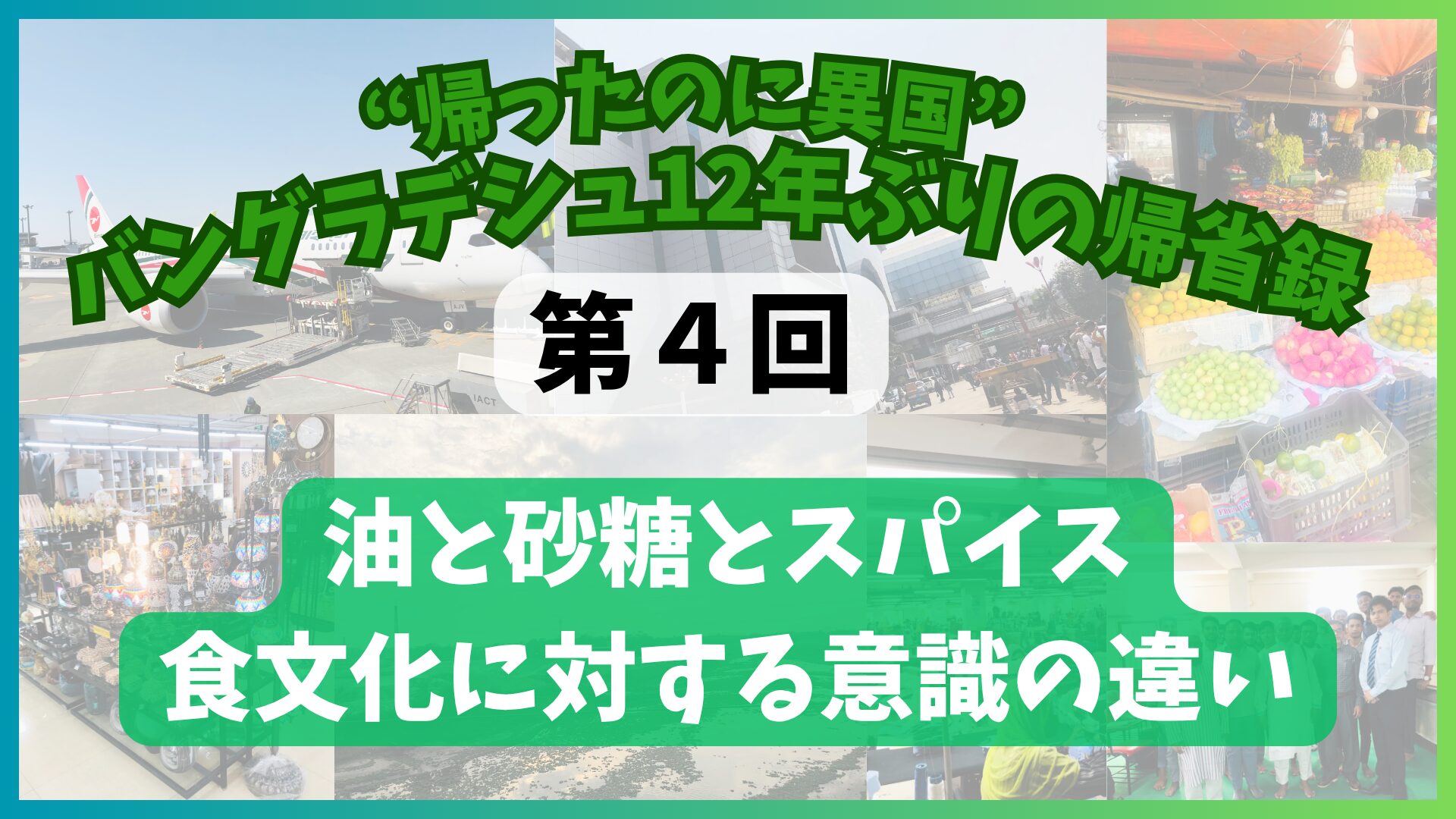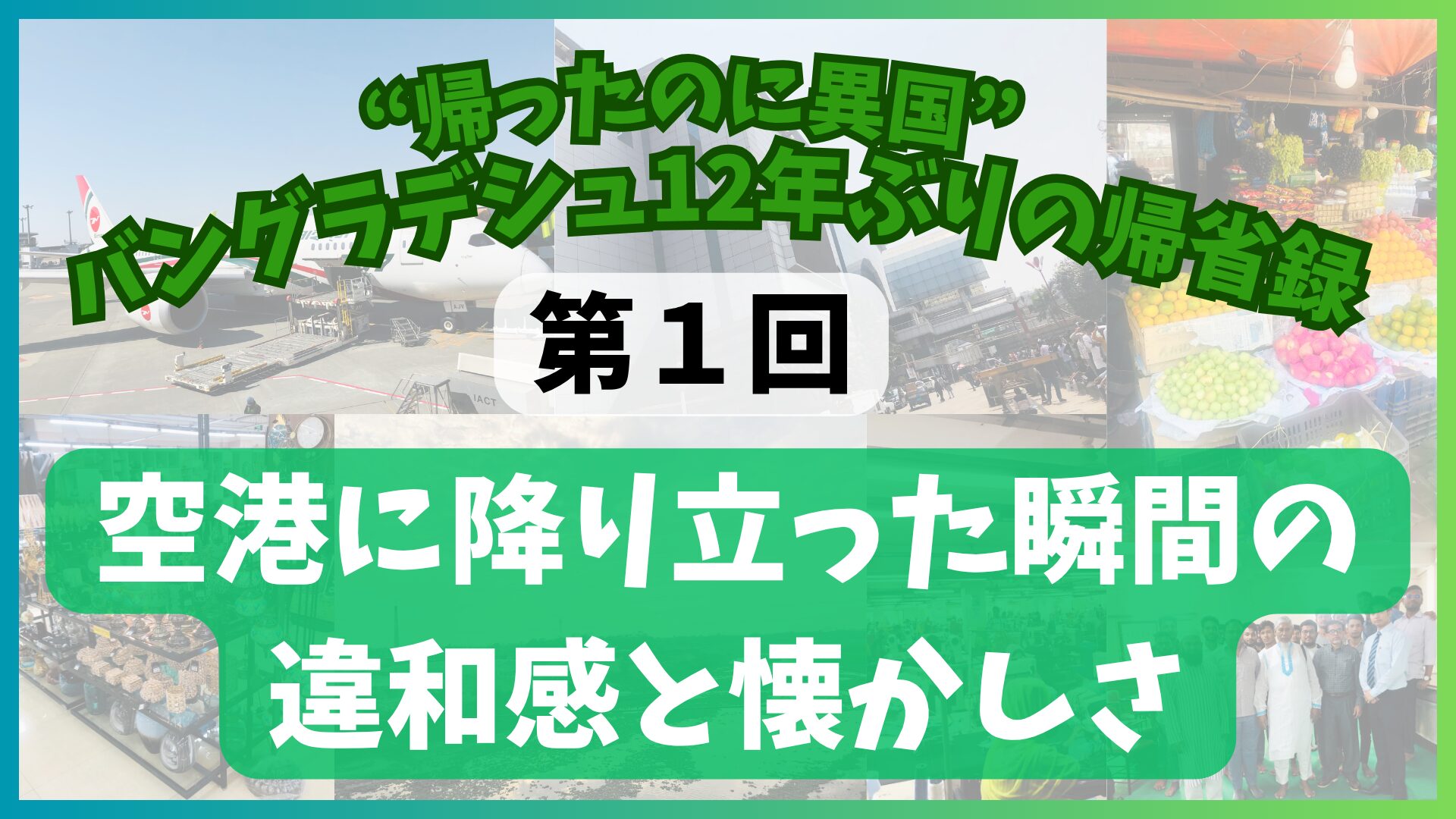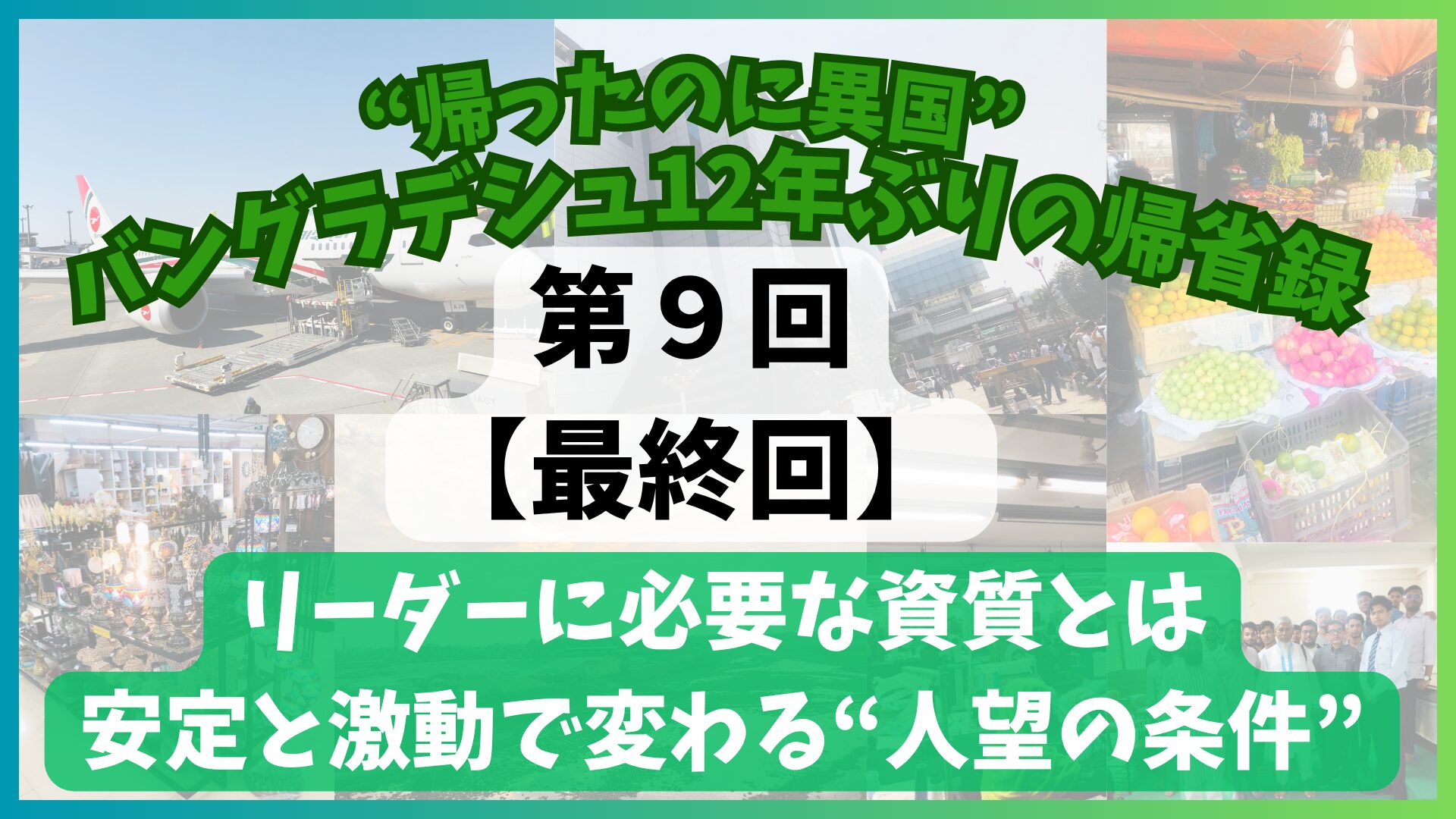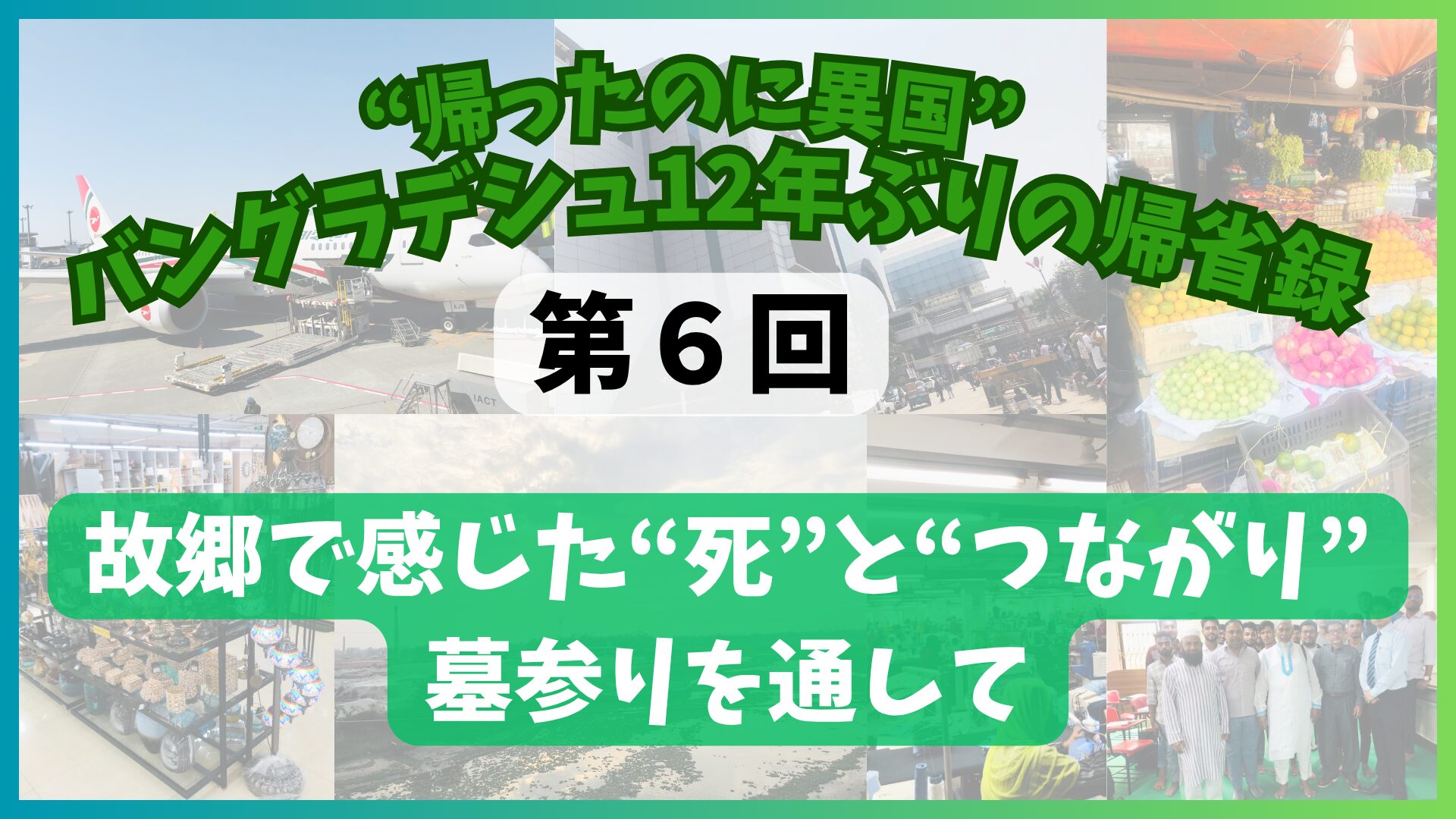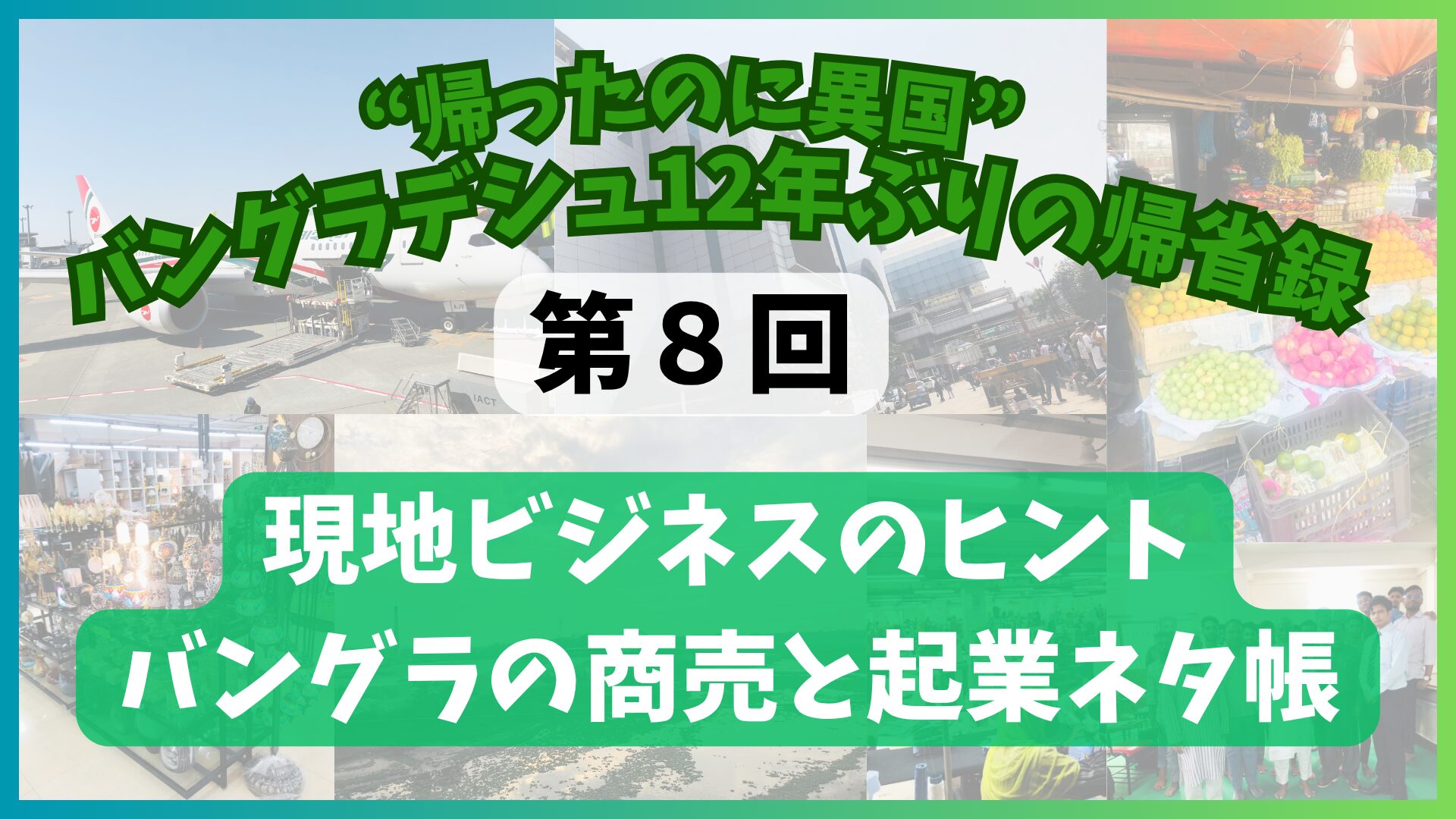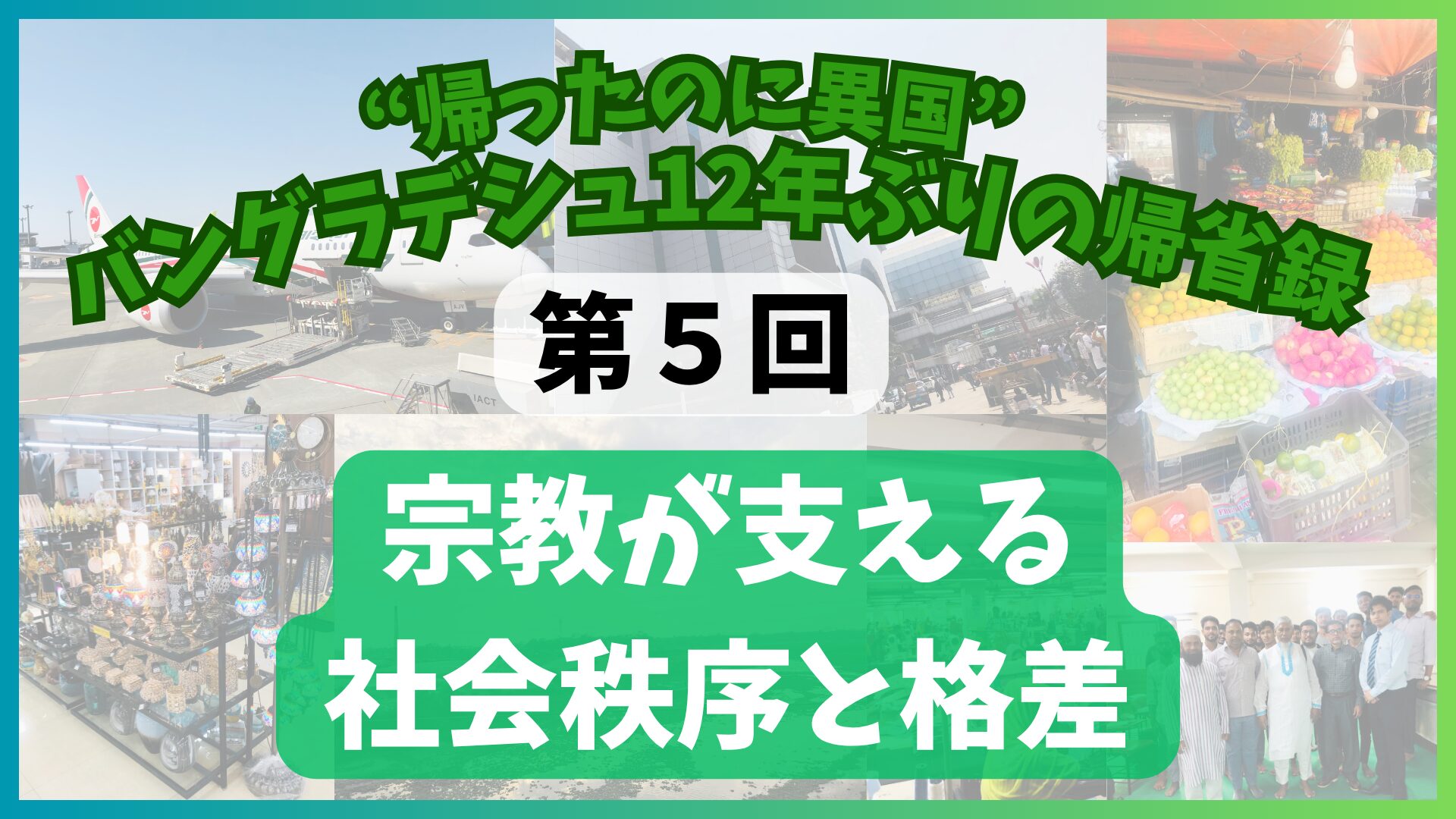【第7回】土地は分割され続ける 先祖の資産を守るという戦い “帰ったのに異国”バングラデシュ12年ぶりの帰省録
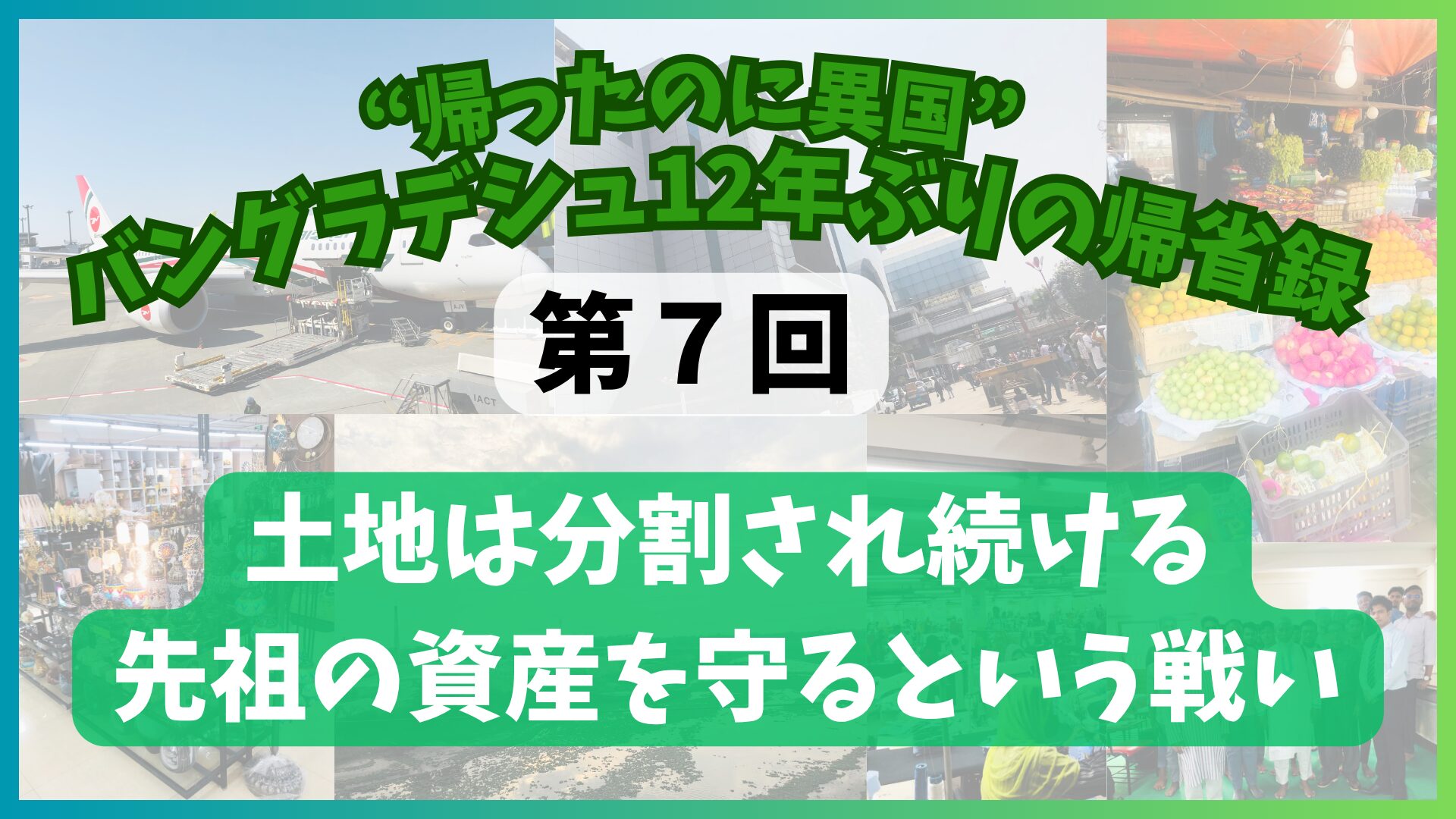
どうやら自分の先祖は大地主だったらしい。
バングラデシュに帰省したとき、父から土地の話や相続トラブルの経緯を聞く中で初めて知った。
とはいえ、大地主だったのはずっと昔の話。現在の土地は当時に比べればごくわずかだ。
それでも、自分が今ここに生きていられるのは、先祖たちが資産を残そうと努力してくれたおかげだ。感謝したい。
土地というのは、資産の中でもとりわけ目に見えてわかりやすい。
ただ、それ以外にも、金や株、債券、時計、絵画、さらには知識や教養といった無形資産もまた、次世代へ引き継がれていく。
自分自身の身体も、遺伝子という意味では資産の継承かもしれない。
きっと誰もが何かしら先祖から受け継いだものを持っている。
ただ、特に土地の相続の場合、“分割”という宿命を背負っている。
人口が増えていく局面では代を重ねるごとに相続人が増え、土地は細切れになっていく。
実際にトラブルの話を聞いていて、「これは面倒な問題だな……」と思った。
同時に、じゃあ逆にどんな土地活用ができるのかも考えてみた。

土地って揉め事多いですよね〜
「土から離れては生きられないのよ。」
ーーシータ「天空の城のラピュタ」より
今、自分がどこに立っているかを考えてみてほしい。
人は空の上にも海の上にも住めない。どこかしら“地面”の上に立っている。
たとえ空を飛べても、作物は空では育たない。
火星に移住したところで土と水はいる。
土地が人類の生活に組み込まれたのは、紀元前3000年ごろの農業革命とされている。
定住が可能になり、集落が生まれ、そこに“所有”の概念が登場した。
結果として格差が生まれ、土地を巡る争いが人類史を動かしてきた。
寒冷地よりも温暖で作物の採れる土地を選ぶのは、生き物として自然な選択だ。
バングラデシュはヒマラヤから流れる豊富な水源を持ち、国土のほとんどが肥沃なデルタ地帯だ。
南アジア一帯は川が多く、温暖な気候に恵まれている。
古代インダス文明から人々がここに住み続けてきたのも、土地と気候のおかげだろう。
土地の“価値”とは何か
都市部で育った自分にとって、土地とは「建物を建てる場所」くらいの認識だった。
家、マンション、学校、病院、商業施設、せいぜい駐車場。
でも田舎に帰ってみて、土地の多様性に驚かされた。
使い方はたくさんある。
・稲を植えて農業
・バナナの木を植えて果物栽培
・木を育てて林業
・池を掘り稚魚を育てて養殖業
・牛や鶏を飼う酪農
・地熱や太陽光を活用した再生エネルギー事業
・村内観光やエコツーリズム施設の整備
・倉庫や工場用地としての活用
実に多様だ。
土地は活かして初めて価値を持つと実感した。
土地は増えない。だが、人は増える。
土地は有限だが、人口は増え続けてきた。
その結果、土地はどんどん分割されていく。
「ここからここまではうちの土地だ」
利権の人間が増えるといざこざも増える。


守るだけでは、土地は減っていく
土地の資産価値は、“放っておけば減っていく”。
守っているだけではやがて分割されてしまい、結果的に目減りしていく。
どこかで「拡大」や「再集約」の力が必要になる。
相続は長男が行なっている場合が多い。
日本でも相続トラブルの多くは次男や三男の立場から生まれる。
かつては、間引き的な発想で次男以下が戦地に送られていたとも聞く。
次男以降は先祖の資産だけを相続し守るよりも新しい資産や価値を生み出さなければならない立場という考え方もできる。
「資産を生み出さなければならない」というプレッシャーは、特に資産の目減りが進む世代や、経済基盤の脆弱な途上国において、より強く表れるのかもしれない。
(かく言う私も次男である)
分割の果てに残るものは──
そもそも、土地の価値は面積や価格だけではない。
一族が築いてきた誇り、名誉、そして「この地に住み継いできた」という時間の重みがある。
けれども、それらもまた、世代を経て分割されることで少しずつ薄れていく。
目に見える土地が細切れになるのと同じように、目に見えない価値も風化していくのかもしれない。
男系による継承は、かつての社会構造や家制度の中では理にかなっていたのだろう。
だが、これからの時代において、それが常に最善とは限らない。
引き継ぎ手や管理者がいなければ、その土地は企業に買収されるか、国が管理するか、あるいは静かに自然へと還っていく。
終わりに 土地は誰のものか?
土地が必要なのは、人間だけではない。
海の中にも海底はあり、地球上すべての生物にとって土地は命の土台になる。
人間が占有している土地には他の大型動物がいない。
「ここは我々の土地だ」
これから日本は人口が減っていく時代に入る。
バングラデシュや世界人口も、所得の上昇とともに人口爆発は頭打ちとなり減少すると言われている。
その時、土地の意味も活用方法も、大きく変わるかもしれない。
自分が次世代に残せるものは何だろうか。
物理的な土地だけではなく、知識や信頼、あるいは歴史といった「無形資産」こそ、これからはより重要になっていくのではないか。
そんなことを考えさせられた帰省だった。